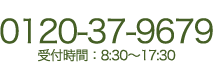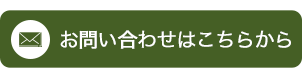認知症予防はいつから始める?(食事編・魚)
認知症とは、脳の病気や障害によって脳の認知機能(記憶力・判断力・思考力など)が低下し、日常生活に支障をきたした状態のことをいいます。
認知症の中で最も多いタイプは「アルツハイマー型認知症」ですが、その原因物質である「アミロイドβ」の蓄積は20年ほど前から始まっているとされています。70歳でアルツハイマー型認知症を発症したとすると、50歳頃からの生活習慣がもう影響しているということです。そのため、認知症予防は早めに意識することが大切です。
アルツハイマー病に限らず、脳卒中は脳内の血管の老化に始まるのでやはり血圧の管理や食生活などが重要ですね。
日々の生活習慣の積み重ねが、未来の自分の身体をつくります。
認知症に限らず、さまざまな病気を予防するために早いうちから健康に良い生活習慣を心がけましょう。
認知症予防になる9つの食べ物
認知症の発症リスクを軽減する可能性がある、代表的な食べ物9つとその栄養素や効果、1日の摂取量目安や調理方法などをご紹介します。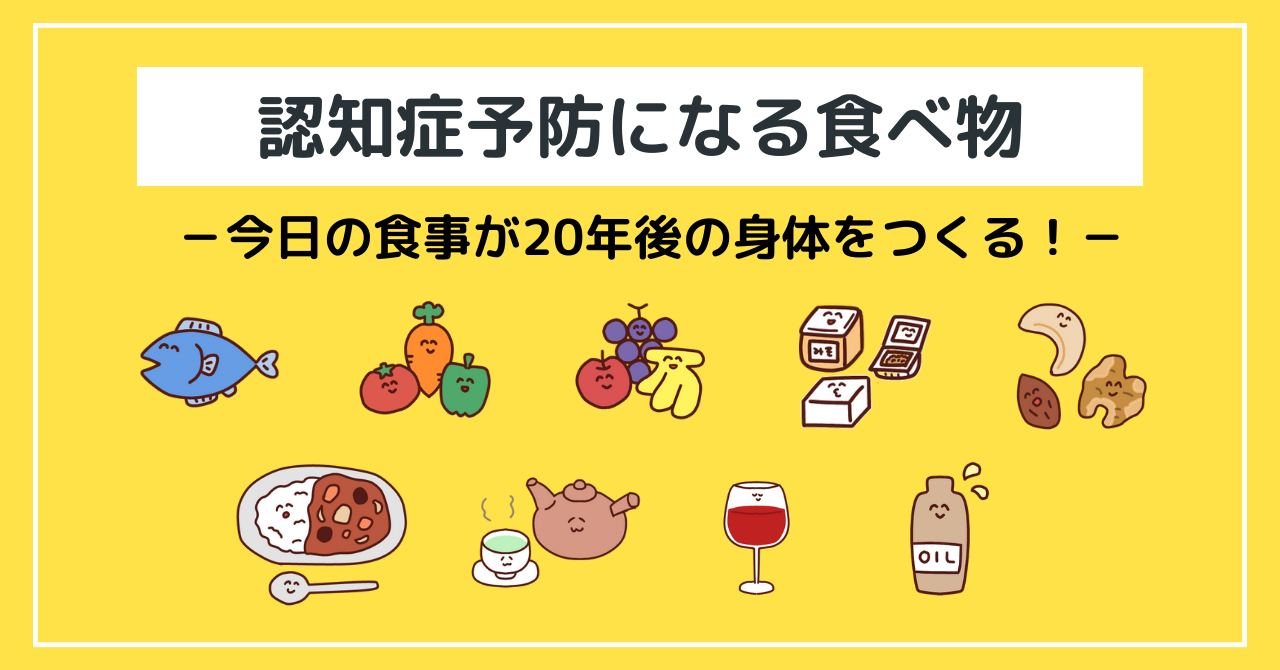
- 魚
魚(とくに青魚)は、脳神経の機能に関わる「オメガ3系脂肪酸」の「DHA」と「EPA」が豊富に含まれています。オメガ3系脂肪酸は、必須脂肪酸とよばれ体内でつくることができないため、食品から摂取する必要があります。
特に旬の魚は脂乗りが良く美味しいうえに、DHA・EPAを多く含んでいます。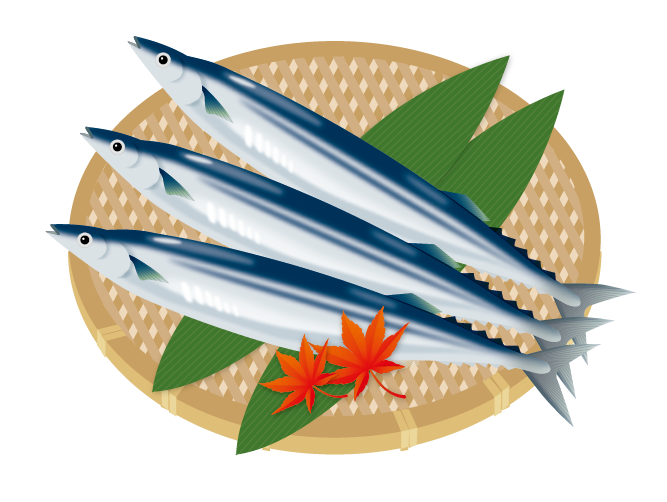
今年は、さんまが豊漁のようで、お求めやすい価格になっていますね。
お刺身は脂を丸ごと摂取できるのでおすすめの食べ方です。焼き魚や煮魚、缶詰だと手軽に毎日の食事に取り入れやすいですね。
<魚の栄養・効果・食材>
DHA :脳の神経細胞の膜の構成成分、認知機能が低下しにくい
EPA :中性脂肪・コレステロール低下、血液サラサラ効果
食材 :さば、いわし、さんま、あじ、鮭 など
食べ方 :お刺身、焼き魚、煮魚、缶詰 など